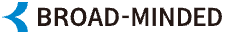ファイナンシャルプランナーへの相談、意味ない?理由や注意点、相談のポイントとは
 その他
その他
「ファイナンシャルプランナー(FP)に相談しても意味がない」「思ったようなアドバイスがもらえなかった」と感じたことはありませんか?確かに、FPの選び方や相談の仕方を間違えると、期待していた答えが得られず悩みが解決できなかったり、かえって不安が大きくなる場合があります。
しかし、適切な方法で相談することで、家計の見直しや将来設計に役立つアドバイスを受けられます。
本記事では、「ファイナンシャルプランナーに相談しても意味がない」と感じる理由や、自分に合ったFPの選び方、注意点を解説します。
「お金の悩みを誰かに相談したいけれど、どうすればよいかわからない…」という方は、ぜひ読み進めてみてください。
マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
目次
ファイナンシャルプランナーに相談しても意味がない理由とは?
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家であり、家計の見直しや資産運用、保険、住宅ローン、相続対策など、幅広い分野の相談をすることができます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合、「FPに相談しても意味がない」と感じてしまう可能性があります。
- ・FPが自分の相談内容に詳しくない場合
- ・資産運用の具体的な相談ができない場合
- ・個別の税務や法律の相談がしたい場合
相談しても意味がない理由①:FPが自分の相談内容に詳しくない場合
ファイナンシャルプランナーの資格には国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士」と民間資格の「AFP」「CFP」などの種類があります。いずれにも共通するのは、非常に幅広い範囲の勉強が必要ということです。
例えば、FPが扱う分野は以下のようなものがあります。
- ・家計の見直し
- ・ライフプラン
- ・保険
- ・投資
- ・不動産
- ・相続
- ・税金 など
しかし、多くのFPはすべての分野に均等に精通しているわけではありません。実際の現場では、特定の分野に強いFPもいれば、そもそも実務経験が浅く、知識が不足しているFPもいます。
FPがどの分野を得意とするかは、所属する企業やこれまでの実務経験によって異なります。そのため、相談する際は「どのような悩みを解決したいのか?」を事前に整理し、それに合ったFPを探すことが重要です。 FP個人の経歴を選べないサービスを利用する場合は、所属する企業の実績等を確認することで、その会社のFPが得意とする分野を把握することもできます。
また、相談内容をできるだけ具体的に記載すると、より自分の悩みに合ったFPを紹介してもらえる可能性が高まります。
例えば、「保険の見直しがしたい」「NISAを始めたいが、何から手を付ければいいかわからない」など、事前に相談したいテーマを整理しておくと、スムーズに適切なFPとつながることができます。
相談しても意味がない理由②資産運用の具体的な相談ができない場合
資産運用の話をメインに相談したい場合、「ファイナンシャルプランナーに相談しても意味がなかった」と感じるケースがあります。
なぜなら、投資商品について具体的な説明や提案をするには、FP資格とは別に「証券外務員」などの専門資格が必要だからです。FP資格のみ保有している人ができるのは、NISAやiDeCoなどの仕組みや、投資に関する一般的な情報の提供などに限られ、具体的な金融商品の紹介や購入のサポートはできません。
また、FP個人が資格を持っていても、所属する会社が金融商品の販売資格を持っていない場合、契約までのサポートができないケースもあります。この点は、保険の相談にも共通する問題で、FPが提案できる保険商品が限られていると、より適した選択肢があっても紹介してもらえない可能性があります。
実際に投資商品や保険を契約するかどうかに関係なく、そうした実行のプロセスまで理解しているFPの方が、より実践的なアドバイスができる傾向があります。
そのため、資産運用や保険の相談をする際は、FPが所属する会社がどういった金融機関と提携しているかも確認してみましょう。
さらに、相談時に「具体的な商品の説明を聞きたい」「購入や契約のサポートまでしてほしい」といった要望を明確に伝えることで、より適切なアドバイスを受けやすくなります。
相談しても意味がない理由③:個別の税務や法律の相談がしたい場合
FPはお金の専門家ですが、相談したい内容が「独占業務」に該当する場合、税理士や弁護士などほかの有資格者でなければ対応できない場合があります。
例えば、以下のような相談はFP単独では対応できません。
- ・具体的な税額計算や確定申告の代行 → 税理士が担当
- ・遺言書の作成や遺産分割のトラブル対応 → 弁護士が担当
ただし、すべての節税や相続対策がFPの範囲外というわけではなく、家計に活用できる控除制度の案内や、保険や不動産を活用した相続対策など、FPがアドバイスできる領域もあります。
また、FPは税理士や弁護士など、さまざまな仕業の専門家と連携しており、必要に応じて紹介してもらうこともできます。「どこに相談すればいいかわからない…」という場合でも、FPを窓口として利用するのは有効な方法です。
相談しても意味がないファイナンシャルプランナーの特徴
ひとくちにファイナンシャルプランナーといっても、保有資格や実務経験、専門知識などが全く異なります。
ご自身の悩みに関係する知識を持っていなかったり、実務経験が浅かったりすると、相談しても悩みが解決せず「意味がない」と感じるかもしれません。
ここでは、相談しても意味がないと感じるファイナンシャルプランナーの特徴についてまとめました。どのようなFPを選ぶべきかも併せて解説します。
知識が浅く、実務経験が少ないFP
FP資格を持っているからといって、必ずしも実務経験が豊富とは限りません。
資格はFPの知識レベルを測る一つの指標にはなりますが、それだけで実力を判断するのは難しいのが実情です。
例えば国家資格の「ファイナンシャル・プランニング技能士」は1級から3級の3段階があり、3級の合格率は80%以上と高く、所得自体はそれほど難しくありません。
また、2級まではFPとしての実務経験がなくても合格できてしまうため、資格を持っていても実務経験が乏しい可能性があります。資格やそれを取得するための専門知識は大切ですが、実務経験もバランスよく有しているFPを探すことが大切です。
例えば、FP資格のランクが高くても年間20件しか相談を受けていないFPと、資格のランクは低くても年間100件の相談をこなしているFPでは、提案の質や対応力に大きな差が出ることがあります。
そのため、資格の有無やランクだけでなく、「どれくらいの相談経験があるか」や「どの分野の相談を得意としているか」を確認しましょう。
古い情報しか持っていないFP
お金に関する制度や法律は、NISA・iDeCoのルール変更、税制優遇の変更など、毎年のように変更されています。そのため、最新の知識を持っていないFPに相談すると、制度に合った適切なアドバイスが受けることができない可能性があります。
国家資格のファイナンシャル・プランニング技能士は、受験時の最新の法律や制度をもとに試験が行われるため、技能士に合格したばかりのFPなら最新の制度や法律の知識を持ち合わせている可能性が高いです。ただし、2025年現在、更新制度はありません。
最新の税制を勉強しているFPも多くいますが、なかには資格を取得したときの知識で止まってしまっているFPがいるかもしれません。
一方で、CFPやAFPなどの民間資格には更新制度があり、定期的に研修を受ける必要があるため、これらを持つFPは最新の情報を持っている可能性が高いといえます。
ただし、資格の有無や種類だけでFPの実力を判断するのは難しく、実際に相談してみないと分からないことが多いのも実情です。
「このFP、言っていることが古い気がする」「最新の情報を知っているのか不安」と感じた場合は、FPに直接確認してみたり、担当を変更したり、別のFPにセカンドオピニオンを求めたりするのも一つの方法です。複数の視点を持つことで、より納得のいく判断がしやすくなるでしょう。
特定の得意分野以外の専門知識を持ち合わせていないFP
ファイナンシャルプランナーのなかには、特定の分野の知識のみ詳しい、というケースがあります。
例えば、保険会社や住宅メーカーに所属するFPは、自社商品の販売促進を目的としてFP資格を取得していることが一般的なため、保険や住宅に関する知識は豊富でも、それ以外の分野には詳しくない場合があります。
そのため、「特定の商品について詳しく解説してほしい」という場合には適していますが、もっと幅広い視点でお金の相談をしたい場合には、少し物足りなく感じることもあります。例えば、「保険を見直さなきゃ」と思ってファイナンシャルプランナーに相談したところ、実は老後の生活資金全体を考えた方が良いと気づき、資産運用や貯蓄のバランスを見直すことになった、というケースもあります。
こうした総合的なアドバイスを受けるには、特定の分野だけでなく、幅広い知識を持つFPに相談するのが有効です。
「もっと広い視点でお金の相談をしたい」「他社の商品も含めて検討したい」という独立系のFPを検討しましょう。所属企業のしがらみがなく、広範囲の知識を得ていることが期待できるため、ライフプラン全体を考慮しながら、幅広い選択肢の中から適切な提案をしてもらえる可能性があります。
商品の勧誘にばかり熱心なFP
FPは、相談者の悩みに寄り添いながら、金融商品の提案を行うことが一般的です。ただし、相談者の意向を無視して特定の商品を強引に勧めるFPには、それ以上の相談をしないほうが良いでしょう。
例えば、「保険を見直したい」と相談した際に、不必要な保障を削減しつつ、「万が一に備えて、この部分は残しておいたほうがいいですね」といったバランスの取れた提案をしてくれるFPは、信頼できるといえるでしょう。
FPが開催する勉強会やセミナーは無料で参加できるケースが多いですが、それは利用者からは参加費を受け取らず、金融商品の販売によって収益を得るスタイルが一般的なためです。しかし、信頼できるPであれば、「本当に必要なものだけを提案し。不要なものは勧めない」というスタンスで対応してくれます。
「このFP、商品の話ばかりしていて、私の悩みをあまり聞いてくれないな…」と感じたら、担当変更を依頼したり、別のFPの意見を聞いてみたりするのも一つの手です。
FP相談で解決できること
ここまで「FPへの相談は意味がない」と感じてしまう理由や、相談しても満足できないFPの特徴などを解説してきましたが、本来FP相談は非常に有意義なものです。
お金に関する法律や特例、家計の見直し、保険、住宅購入、相続対策など、幅広い知識を持つFPに相談できれば、お金に関する悩みを解決できる可能性は十分にあります。
ここからは、実際にFPに相談できる内容と、その料金相場について解説します。
ファイナンシャルプランナーへの相談が多い分野とは?
日本FP協会「ファイナンシャル・プランナー実態調査結果報告書」によると、もっとも相談が多い分野はライフプランニング(38.7%)でした。以下、6つの分野で相談が多い順に並べると以下のとおりになります。
- ・ライフプランニング(7%)
- ・相続・事業承継設計(8%)
- ・金融資産運用設計(4%)
- ・タックスプランニング(3%)
- ・保障・補償設計(7%)
- ・不動産運用設計(9%)
- ・リタイヤメントプランニング(8%)
- ・その他(3%)
「今の収入と支出で、将来のお金は足りるのか?」「子どもの教育資金や老後資金はどう準備すると良いのだろう?」といった長期的なお金の管理(ライフプランニング)についての相談や「親が亡くなったら相続税はどれくらいかかる?」といった相続についての相談が多く寄せられています。
ファイナンシャルプランナーに相談するときの料金の相場は?
FP相談には、無料相談と有料相談の2つの方法があります。
日本では無料相談が一般的ですが、有料で相談を受け付けているケースもあります。
日本FP協会「ファイナンシャル・プランナー実態調査結果報告書」によると、有料のFP相談の費用の平均は以下のとおりです。
【1時間あたりの相談料の平均】
| 1時間あたりの相談料 | 平均 |
| 2,000円未満 | 2.8% |
| 2,000円~3,000円未満 | 3.6% |
| 3,000円~4,000円未満 | 7.1% |
| 4,000円~5,000円未満 | 0.7% |
| 5,000円~6,000円未満 | 37.0% |
| 6,000円~7,000円未満 | 3.9% |
| 7,000円~8,000円未満 | 1.1% |
| 8,000円~9,000円未満 | 4.6% |
| 9,000円~10,000円未満 | 0.7% |
| 10,000円~20,000円未満 | 33.5% |
| 20,000円以上 | 5.0% |
出典:日本FP協会|2021年度ファイナンシャル・プランナー実態調査結果報告書
有料のFP相談は、1時間当たり5,000~6,000円がもっとも多く、次いで1万円~2万円未満が多い結果になりました。
さらに、提案書をFPに作成してもらう場合、平均43,000円程かかるのが一般的です。
有料相談のメリットとしては、相談料を収益源としているため、特定の商品を勧められにくいことが挙げられます。
ただし、FP相談は1回の面談に1~2時間かかり、さらに複数回の面談が必要になることも多いため、金銭的・時間的なコストを負担に感じることもあります。
一方で、無料で相談できるFPサービスも数多くあり、手軽に専門家のアドバイスを受けられるのが魅力です。
「まずは気軽にFPに相談してみたい」「継続的に無理なく相談したい」という場合は、無料相談を活用するのも一つの方法です。
ファイナンシャルプランナーに相談できることのメリット
ご自身の悩みに寄り添ってくれるだけの専門知識と実務経験があるFPに相談することで、実にさまざまな悩みを解決に導くことができます。
FPに相談することのメリットをまとめると、以下のとおりです。
- お金に関するあらゆる悩みについて相談できる
- 家計の見直しをすることで経済的な負担を軽減し将来に備えられる
- 専門家に相談することで安心して今後のプランを考えられる
ここからは、FPに相談することのメリットについて詳しく解説します。
メリット①お金に関するあらゆる悩みについて相談できる
FPに相談することのメリットは「お金に関するあらゆる悩みを一括して相談できる」ことです。
お金の悩みは、「家計を見直したい」「教育資金の準備方法がわからない」「老後の資金が足りるか不安」「資産運用を始めるべき?」など、複数の問題が絡み合っていることがほとんどです。
例えば、「住宅ローンを見直したい」と思って相談したら、実は老後資金の計画も見直す必要があった、というケースもあります。
FPは、こうしたお金に関するさまざまな課題を整理し、優先順位をつけて、どこから改善すればいいかをアドバイスしてくれるのが大きな強みです。
相談者自身では気付けなかった家計や将来の課題を、客観的な視点から専門的なアドバイスをしてもらえるでしょう。
「なんとなく不安だけど、何をすればいいかわからない」という段階でも、FPと話すことで問題を整理し、やるべきことが明確になります。
メリット②家計の見直しをすることで経済的な負担を軽減し将来に備えられる
FPは、家計の見直しや節約についても精通しています。
「節約しなきゃ…」と思っても、どこをどう削ればいいのか、自分では意外とわからないものです。
FPは、家計の現状を客観的に分析し、ムリなく続けられる改善策を提案してくれます。
例えばFPの相談業務では、「家計の収支確認表」に顧客の年間収入と支出を記入することで、年間でどれくらいの赤字(または黒字)が出ているか明らかになります。
また、家庭の資産や借金を「家計のバランスシート」に入力することで家計の健全度を確認したり、キャッシュフロー表で現在から将来までのお金の流れが健全かを診断することができます。
単なる節約アドバイスではなく、「不要な保険を見直す」「住宅ローンの借り換えを検討する」「将来のために貯蓄と投資のバランスを考える」など、具体的な方法を示してくれるのがFPの強みです。
家計の見直しをすることで、無理なく支出を最適化しながら、将来の資金計画も立てられるのが、大きなメリットです。
メリット③専門家に相談することで安心して今後のプランを考えられる
お金に精通した専門家に相談することで、安心感が生まれるのもFP相談のメリットです。
FPは「家計のホームドクター」と呼ばれることもあり、お金に関してさまざまな知識を持っています。
お金のことを一人で考えていると、「この選択で本当に大丈夫?」「もっと良い方法があるのでは?」と迷いが出てしまい、行動に移せないこともあります。
FPに相談することで、節約や家計管理の方法だけでなく、最新の給付金など公的な制度も含めた具体的なプランを提案してくれるため、自信を持って将来に備えることができます。
FPは税理士や弁護士などの専門家と連携していることが多いため、必要に応じて適切な専門家を紹介してもらえるのもメリットのひとつです。
ファイナンシャルプランナーに相談する前に知っておきたいコツと注意点
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家ではありますが、どのような知識や経験を持っているかは千差万別です。相談相手を間違えると悩みを全く解決できなかったり、かえって不安になったりする可能性もあります。
ここからは、FPに相談する際に知っておきたい、FP選びの注意点を紹介します。
相談前に、自分の悩みや目的を整理しておく
FPに相談するとき、「何について相談したいか?」をざっくりでも整理しておくと、話がスムーズになります。
FPにもさまざまな得意分野があるため、事前に相談内容を伝えておくことで、自分の悩みに合ったアドバイスを受けやすくなるでしょう。
とはいえ、細かい内容まで決めておく必要はなく、「教育費の準備方法が知りたい」「住宅ローンの借り換えの相談がしたい」「保険の見直しをしたい」といったざっくりした内容が決まっていればOKです。
それだけでも、FP側が相談の方向性をつかみやすくなり、場合によっては事前に準備をしてくれることもあります。
一方で、「お金のことを相談したいけど、具体的に何を聞けばいいかわからない…」という人もいるでしょう。
その場合は、「なんとなく将来のお金が不安」「今の家計のままで大丈夫なのか知りたい」といった漠然とした悩みでも問題ありません。
FPの役割は、相談者の状況を整理し、何を考えるべきかを一緒に見つけることでもあります。むしろ、「何が問題なのか分からないから相談したい」というのも立派な相談理由です。
「しっかり準備しなきゃ」と気負わず、まずは気軽に相談してみましょう。
継続的なサポートを受けられるFPを選ぶと安心
FPのサポートは、一度の相談で終わるものではなく、長期的にサポートを受けることで本当の効果が出るといわれています。
しかし、FPが提供しているサービスや所属する企業によって、アフターフォローの有無やサポート期間が異なる場合があるため注意が必要です。
せっかく信頼できて自分の悩みに的確なアドバイスを受けられるFPを見つけたとしても、契約後の手続きや見直しのタイミングでサポートを受けられないと不安が残ってしまうこともあります。
また、FPが独立して活動している場合や、担当FPが転職・退職した場合、その後のフォローが途切れてしまう可能性もあります。
その点、アフターフォローの仕組みが整っている企業であれば、FPが退職した後でも、専任のサポートチームが引き継ぎを行い、契約後の手続きまでしっかりサポートしてくれるため安心です。
さらに、全国対応のサービスなら、転居後も引き続き相談ができるため、ライフステージの変化に合わせた見直しがしやすいというメリットもあります。
大切なお金の不安を相談するなら、オンライン相談が可能で、アフターフォローの体制が整っているFPを選ぶのが安心です。
まとめ
「ファイナンシャルプランナーへの相談には意味がない」と言われることもありますが、これは相談するFPが自分の悩みに合っていなかったり、期待していたアドバイスが得られなかった場合に起こることがほとんどです。
一方で、家計の見直しや将来設計をサポートしてくれるFPに出会えれば、大きなメリットがあります。
ファイナンシャルプランナーを選ぶ際には、自分が抱えている悩みに精通しているか、必要に応じて他の専門家とも連携できるかといったことを確認しましょう。
「お金のことを相談したいけれど、誰に聞けばいいかわからない…」「気軽に話せるFPがいればいいのに」と感じているなら、無料で相談できるFPサービスを活用するのも一つの方法です。
まずは一度相談してみることで、自分に合ったFPと出会い、将来のお金の不安を減らしていきましょう。
マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
- ID:BM–684