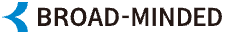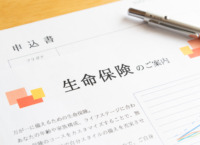妊娠中に保険は入るべき?知っておきたい出産前後の費用とリスクを解説
 生命保険
生命保険
「妊婦は保険に加入しておいた方が良いの?」「妊娠や出産にはどのようなリスクがある?」
現在妊娠中の方やこれから妊娠を考えている方の中には、このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、妊娠・出産には想定外のトラブルが発生する可能性もあるため、保険に加入しておくことがおすすめです。
この記事では、妊婦が保険に加入しておくべき理由や妊娠・出産にあたって考えられるリスク、そして妊娠・出産にかかる費用について解説します。
また、医療保険が活用できるケースや妊婦が医療保険に加入する際の注意点に関しても触れているため、ぜひ最後まで読んで知識を深めてください。
マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
妊婦が保険に加入しておくべき理由
妊娠・出産には、さまざまな要因によって入院したり、手術を受けたりするリスクがあります。
特に、入院をすることとなった場合は、入院期間が長引くケースも少なくありません。
妊娠・出産に伴う金銭的な負担に備えておくためにも、妊婦は保険に加入しておくことをおすすめします。
中でも、妊婦が加入を検討するべき保険は「医療保険」です。
一般的に、医療保険では、健康保険が適用される入院や手術、処置を受けた際に給付金が受け取れる可能性があります。
ただ、どのようなケースのときに給付金が受け取れるのかは保険会社によって異なるため、実際に給付金を請求する際はFPなどに確認しておきましょう。
なお、医療保険は年齢が若いときに加入した方が保険料は割安になります。
病気をしてしまうと保険に加入できなかったり、保険料が高くなってしまったりすることもあるため、年齢が若く健康なうちに医療保険への加入を検討しましょう。
妊娠・出産にあたって考えられるリスク
妊娠・出産にあたっては、さまざまなリスクが伴うことを意識しなければなりません。
主に考えられるリスクは以下の6つです。
- ・妊娠悪阻(つわり)
- ・切迫流産・切迫早産
- ・妊娠高血圧症候群
- ・妊娠糖尿病
- ・異常分娩
- ・マタニティブルー
それぞれどのような状態を指すのか解説していきます。
妊娠悪阻(にんしんおそ)
妊娠悪阻とは、妊娠期間中に発生する重度のつわりを指します。
妊娠初期においては、吐き気や嘔吐などのつわりを経験する妊婦の方が多いです。
しかし、妊娠悪阻の場合は、強い吐き気・激しい嘔吐によって水分補給すらできなくなる状態に陥り、極端な体重減少や脱水症状を引き起こします。
このような状態が継続すると、母体のみならず胎児にも危険が及ぶことが考えられるため、適切な治療を受けなければなりません。
一般的に、妊娠悪阻と診断された場合は通院にて点滴や薬物による治療が行われますが、症状がひどい場合は入院を求められるケースもあります。
切迫流産・切迫早産
妊娠22週未満で妊娠が終了してしまうことを「流産」、妊娠22週以降37週未満で妊娠が終了してしまうことを「早産」といいます。
切迫流産・切迫早産とは、何らかの原因によって流産や早産になりかけている状態のことです。
これらの一般的な治療法は「安静にすること」であるため、医師の指示にしたがって自宅安静もしくは入院で治療を行います。
また、切迫流産や切迫早産で入院が必要となった場合は、妊婦の状態に応じて数日で退院できることもあれば数ヶ月にわたる長期入院が求められるケースがある点には注意しなければなりません。
妊娠高血圧症候群
妊娠高血圧症候群とは、妊娠に伴って血圧が高くなってしまう状態のことです。
収縮期の血圧(上)が140mmHg以上、もしくは拡張期の血圧(下)が90mmHg以上になった場合に診断され、治療を受けなければなりません。
また、妊娠高血圧症候群は以下の4種類に分けられます。
- ・妊娠高血圧
- ・妊娠高血圧腎症
- ・加重型妊娠高血圧腎症
- ・高血圧合併妊娠
これらは、今までに高血圧と診断されたことがあるか、タンパク尿が出ているか、母体に脳卒中や腎臓・肝臓の機能障害が発生しているかなどをもとに診断されます。
一般的な治療法としては、安静にすると同時に降圧剤を服用する薬物療法が主となりますが、タンパク尿が出ているときや収縮期の血圧(上)が160mmHg以上、もしくは拡張期の血圧(下)が110mmHg以上となっているときは、入院が求められることとなるため注意が必要です。
妊娠糖尿病
妊娠糖尿病とは、妊娠に伴って糖代謝異常が起こることをいいます。
妊娠中は血糖値を下げる働きをする「インスリン」の生成機能が落ちることで、通常時と比較して血糖値が高くなりやすい傾向にあります。
妊娠糖尿病になると、妊娠高血圧症候群を併発したり、羊水過多となってしまったりといった母体に対する影響だけでなく、胎児にも心臓肥大や黄疸、最悪の場合は胎児死亡に陥るリスクがある点には注意しなければなりません。
一般的には食事や運動によって血糖値をコントロールすることを目指しますが、それらのみでは数値が改善しない場合は、インスリン注射による治療が必要となります。
なお、妊娠糖尿病になると、将来的に糖尿病になるリスクが高まるため、出産後も定期的に診察を受け状態を確認することが重要です。
異常分娩
異常分娩とは、正常分娩に当てはまらない分娩のことを指し、具体的には以下のような分娩方法が当てはまります。
<異常分娩の種類>
| 内容 | |
| 帝王切開 |
・経膣分娩による出産ができないと判断されたときに行われるもの |
| 鉗子分娩 |
・鉗子(かんし)と呼ばれる医療用器具を用い、胎児の頭を挟んで引き出すことで出産をサポートするもの |
| 吸引分娩 |
・吸引カップを胎児の頭に装着し、引き出すことで出産をサポートするもの |
帝王切開となるケースとしては、出産前に子宮から胎盤が剥がれ落ちてしまう「常位胎盤早期剥離」や胎盤が子宮口を覆っている「前置胎盤」などに加え、母体が妊娠に伴う合併症(妊娠高血圧症候群など)を発症している場合が挙げられます。
また、分娩中に陣痛が弱まって分娩が進まなくなってしまったり、胎児の心拍が急激に低下したりしたときに用いられるのが鉗子分娩もしくは吸引分娩です。
妊娠の経過が良好であったとしても、出産時には何が起こるかわかりません。
上記で挙げたリスクがあることを理解し、保障を準備しておくことが大切です。
マタニティブルー
マタニティブルーとは、妊娠中や出産後に精神的に不安定な状態になることをいいます。
症状としては、涙もろくなると同時に、集中力の低下や気分の落ち込み、食欲不振、倦怠感などが現れ、通常1〜2週間程度で軽快するケースが多いです。
また、マタニティブルーを発症する時期として多いのが、妊娠初期〜妊娠中期、産後3〜10日といわれています。
妊娠・出産をするとホルモンバランスが急激に変化するだけでなく、出産・育児への不安や出産後の生活リズムの大幅な変化によって精神的なストレスを抱えることでしょう。
マタニティブルーは一過性のものであるとはいえ、精神的に辛い状態が続きます。
精神的なストレスを抱えすぎないようにすることが大切です。
妊娠や出産によってかかる費用
妊娠や出産によってかかる費用は、選択する医療機関や妊娠の経過、出産方法などによって大きく異なります。
ここでは、妊婦健診における具体的な検査内容に加え、出産費用の全国平均について見ていきましょう。
また、出産時に利用できる制度に関しても解説していきます。
妊婦健診
妊婦健診とは、母体や胎児の健康状態を確認するために一定期間ごとに受ける健診のことをいいます。
健診ではさまざまな検査等が行われますが、主な内容は以下のとおりです。
<妊婦健診の検査内容>
| 体重測定 | 体重増加の目安※に沿って適切に体重が増加しているかを確認 |
| 血圧測定 | 妊娠高血圧症候群の早期発見に向け、血圧上昇の有無を確認 |
| 尿検査 | 妊娠糖尿病の早期発見に向け、尿タンパクや尿糖の有無を確認 |
| 腹囲・子宮底長測定 | 妊娠週数に応じて子宮が大きくなっているかを確認 |
| 血液検査 | 血液型や血糖、風疹ウイルスへの抗体の有無などを確認 |
| 超音波(エコー)検査 | 胎児の大きさや発育状態、胎盤の位置などを確認 |
| 性器クラミジア検査 | 胎児が産道を通る際に感染する可能性のある細菌に母体が感染していないか確認 |
| B群溶血性レンサ球菌検査 |
※妊娠前のBMIによって異なる
妊婦健診は健康保険の適用外となるため、全て自費での受診となります。
ただし、妊娠をすると母子手帳を受け取る際に、多くの自治体で「妊婦健診に対する助成券」も同時に配布されるケースが一般的です。
この助成券を利用することで自治体が妊婦健診費用を補助してくれるため、無料になるケースもあります。
なお、妊婦健診以外での通院や助成券の対象とならない検査を受けた場合は支払いが発生する点には注意しましょう。
出産費用の全国平均
令和5年度における出産費用の全国平均は以下のとおりです。
<出産費用の全国平均>
| 分娩全体 | 正常分娩のみ | |
| 全施設 | 489,802円 | 506,540円 |
| 公的病院※1 | 427,561円 | 473,990円 |
| 私的病院※2 | 506,572円 | 524,345円 |
| 診療所(助産所を含む)※3 | 513,921円 | 510,754円 |
※1 国公立病院、国公立大学病院、国公立病院機構等
※2 私立大学病院、医療法人病院、個人病院等
※3 官公立診療所、医療法人診療所、個人診療所、助産所
出典:厚生労働省「出産費用の状況等について」
なお、正常分娩による出産費用の平均が最も高かったのは東京都で625,372円※、最も低かったのは熊本県で388,796円※でした。
※出典:厚生労働省「出産費用の状況等について」
これらのデータから見てわかるとおり、出産する医療機関やその医療機関の所在地によって、出産費用は大きく異なります。
事前に医療機関のホームページを確認したり、直接問い合わせたりすることで、具体的な費用をイメージしやすくなるでしょう。
出産時に利用できる制度
出産時に利用できる制度としては、主に以下のものが挙げられます。
<出産時に利用できる制度>
| 出産・子育て応援事業 | 自治体が主体となって行う給付事業で、妊娠届を出したときに5万円、出生届を出したときに5万円が受け取れる |
| 出産育児一時金 | 胎児一人あたり50万円(全国一律) |
上記以外にも、出産手当金や育児休業給付金などの受け取りが可能です。
ただし、出産手当金を受け取れるのは、出産した本人が会社の健康保険の被保険者である場合に限られます。
また、育児休業給付金は、育児によって休業する本人が雇用保険の被保険者でなければなりません。
このように、出産時には出産する本人が雇用保険の被保険者であるか、加入している健康保険の種類は何かによって受け取れる給付が異なる点には注意が必要です。
妊娠・出産で医療保険が活用できるケース
妊娠や出産に伴って医療保険が活用できるケースとしては、以下の2つが挙げられます。
- ・妊娠中に発生したトラブルによって入院・手術を受けたとき
- ・出産時に発生したトラブルによって入院・手術を受けたとき
一方で、正常分娩は健康保険が適用されないことから、医療保険の対象外となる点は覚えておきましょう。
妊娠中に発生したトラブルによって入院・手術を受けたとき
妊娠中に発生するトラブルとしては、先述した妊娠悪阻や切迫流産・切迫早産、妊娠高血圧症候群などが挙げられます。
これらを原因として入院をした場合、医療保険から給付金が受け取れる可能性が高いでしょう。
また、子宮頸管が短くなることによって流産や早産のリスクが高まっているときや子宮筋腫があることによって妊娠に悪影響を与えているときなどは、手術を受けることがあります。
健康保険が適用される手術であれば、給付金が受け取れる可能性が高いです。
なお、加入する医療保険によって支払事由※が異なるため一概にはいえませんが、入院や手術をせずに通院のみで治療を受ける際は、医療保険からの給付金が受け取れません。
※どのような状態のときに給付金が支払われるのかを定めたもの
出産時に発生したトラブルによって入院・手術を受けたとき
出産時に発生するトラブルとしては、主に帝王切開や鉗子分娩、吸引分娩といった異常分娩が挙げられます。
これらの分娩方法が選択された場合は、基本的に医療保険からの給付金の受け取りが可能です。
また、出産後に出血が止まらない「弛緩出血」や胎盤が筋層内まで食い込んで剥がれなくなってしまう「癒着胎盤」などが発生した際には、緊急手術が行われるケースが少なくありません。
これらのケースにおいても、医療保険からの給付金が受け取れる可能性があります。
正常分娩は医療保険の対象外
正常分娩は、健康保険が適用されません。
先述したとおり、一般的に、医療保険から給付金が受け取れるのは、あくまでも「健康保険が適用される入院や手術、処置を受けたとき」です。
そのため、正常分娩での入院等は医療保険の対象外となる点には注意しましょう。
ただし、正常分娩であっても会陰損傷がひどかったり、出産を原因として感染症になり入院が長引いたりした場合は医療保険から給付金が受け取れる可能性があるため、FPに確認することがおすすめです。
妊婦が医療保険に加入する際の注意点
妊婦が医療保険に加入する際の注意点としては、以下の3つが挙げられます。
- ・そもそも加入できない可能性がある
- ・妊婦向けの医療保険は保障範囲が限定されている
- ・妊娠中に加入できたとしても、妊娠・出産に伴う入院や手術が保障されないケースがある
先述したとおり、妊娠・出産はさまざまなリスクと隣り合わせであることから、いつ入院したり手術を受けたりする状況に陥るかわかりません。
そのため、保険会社としては「妊婦は給付金を支払う可能性が高い」と判断し、契約者間の公平性を保つために加入を断る可能性があります。
また、妊娠中でも加入できる妊婦向けの医療保険もありますが、そのような商品は保障範囲が限定されている点には注意が必要です。
加えて、仮に妊娠中に通常の医療保険に加入できたとしても、妊娠・出産に関連する臓器である子宮や卵巣が不担保※となり、それらに関する入院や手術が保障されないケースもあるため気をつけましょう。
※保障が受けられないこと
一般的に、妊娠後期に入る妊娠28週までは加入を検討できるケースがあります。
中には出産直前まで加入可能な医療保険もあるため、現在妊娠中で医療保険に加入していない方は、FPに相談してみましょう。
まとめ
この記事では、妊婦が保険に加入しておくべき理由や妊娠・出産にあたって考えられるリスク、妊娠・出産にかかる費用、医療保険が活用できるケースや妊婦が医療保険に加入する際の注意点について解説しました。
妊娠・出産にはさまざまなトラブルが発生する可能性がありますが、適切な医療保険を選択し加入しておくことで、金銭的な負担を大きく減らすことが可能です。
しかし、医療保険は保険会社によって保障内容や保険料が異なるため、自身にはどのような医療保険が適切なのか判断できないこともあるでしょう。
その際には、保険に関する知識が豊富なFPに相談することで、あなたに適した医療保険が見つかるはずです。
マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
- ID:BM–663