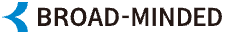ファンドラップで大損?仕組みとリスクを正しく理解しよう
 資産運用
資産運用
近年、注目を集めているファンドラップ。プロに資産運用を一任できる魅力的なサービスですが、「ファンドラップは大損する」「ファンドラップは危険」といった声を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
実際、ファンドラップの手数料や仕組みをしっかりと理解していないと、運用を始めたことを後悔する事態にもなりかねません。
今回の記事では、ファンドラップの仕組みやメリット・デメリットを紹介しつつ、どんな方にファンドラップが向いているのかを丁寧に解説します。
マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
目次
ファンドラップとは?仕組みと基本的な特徴
まずは、ファンドラップとはそもそもどのような仕組みの運用商品なのかを確認していきましょう。
ファンドラップの基本的な仕組み
ファンドラップとは、顧客の資産運用を金融機関に一任し、プロが代わりに運用・管理してくれるサービスのことです。
アンケートなどを用いて投資家のリスク許容度や投資目的などをヒアリングしたうえで、運用ニーズに沿ったポートフォリオや運用方針を提案するという仕組みです。
運用を開始した後は、金融機関が資産配分や投資先の選定、リバランスなどを自動的に行ってくれるため、手間をかけずに継続的な運用を行えます。投資の知識や時間がない人でも、本格的な資産形成を目指せる点も魅力の一つです。
価格変動リスクを抑えながらリターンの安定化を目指す「長期分散投資」を基本として運用されるため、長期的な資産形成に適しています。
ファンドラップと投資信託の違い
ファンドラップと投資信託は、どちらも複数の資産に分散投資を行い、リスクを抑えながらリターンを狙う金融商品です。特に、バランス型の投資信託とは運用スタイルが似ており、定期的にリバランスを行う仕組みも共通しています。
大きな違いは「個別のニーズに合わせた運用ができるかどうか」という点です。ファンドラップでは、契約者ごとにリスク許容度や運用目的に応じて最適なポートフォリオを組むため、より個人のニーズに寄り添った運用が可能です。一方、投資信託はパッケージ化された商品であるため、すべての投資家に同じ運用が適用されます。
また、費用面でも違いがあります。一般的に、ファンドラップの方が手数料が高めに設定されており、投資信託と比べて運用コストは割高となっています。
ファンドラップと投資信託の違いをまとめると、下記の通りです。
| ファンドラップ | 投資信託 | |
| 運用方法 | 投資家に代わって金融機関(プロ)が一任運用する | 投資信託ごとの運用方針に沿ってファンドマネージャーが運用する |
| 投資対象の選定 | 個別のニーズに応じてポートフォリオや運用コースが選択される | あらかじめ決められた資産配分や運用方針で運用される |
| 運用コスト | 高め(投資顧問報酬+投信の信託報酬など) | 相対的に割安(信託報酬のみ、インデックス型ならさらに低コスト) |
| 投資金額の目安 | 数百万円など高額からの運用が一般的 | 数千円~と少額から購入可能 |
| NISA対応 | 原則として非対応 | 一般NISA・つみたてNISAともに対応可(商品による) |
関連記事
ファンドラップのメリット・魅力
続いて、ファンドラップのメリットや人気のある理由を確認していきましょう。
プロに運用を任せられる
ファンドラップの最大の魅力は「運用をプロに任せられる手軽さ」です。
一度ファンドラップを契約したら、運用資産配分の提案から銘柄の選定、売買のタイミング、定期的なリバランスまで、すべてを金融の専門家に任せられるため、手間をかけずに運用を続けられます。
投資の知識や経験が少ない方でも、手間や時間をかけずに本格的な資産運用を行えるのが大きな魅力と言えるでしょう。
複数の資産に分散投資できる
ファンドラップでは、株式、債券、REIT(不動産投資信託)など、さまざまな資産に分散投資することでリスクを抑えた運用を目指します。
仮に、すべての資金をまとめて一つの資産に投資してしまうと、投資先の資産の価値が暴落した場合に自分の資産全体が大きく目減りしてしまうかもしれません。
しかし、異なる値動きをする複数の資産を組み合わせることで、いずれの資産価値が下がってしまっても、その他の資産の値動きで損失分をカバーしやすくなります。
ファンドラップでは、国内外のさまざまな資産をプロの目で選定し、グローバルにリスクを分散する仕組みが取られています。
自分のリスク許容度や求めるリターンに合わせて運用できる
自分の許容できるリスク度合いやパフォーマンスに合わせた運用を行いやすいのもファンドラップのメリットです。
ファンドラップの運用を始める際は、顧客に対してリスク許容度や目標リターンを確認するヒアリングが実施されます。これによって、自分の投資ニーズが明確になり、最適な投資スタイルや運用プランが提示され、納得した形で投資を始めることが可能です。
「どんな商品が自分に合っているのかわからない」と感じている方にも、使いやすいサービス設計となっています。
投資の知識や経験が少なくても始められる
ファンドラップは、投資の知識や経験が乏しい方でも気軽に始められるサービスです。情報収集や分析といった煩雑な作業は不要で、契約後はプロが自動的に運用してくれるため、忙しい人や初心者でも安心して始めやすいでしょう。
また、定期的な運用報告書なども提供されるため、自分の資産状況を確認しやすい点もメリットです。
専任の担当者がつく対面型証券の場合は、営業担当者に相場の状況や運用パフォーマンスについて教えてもらうこともできるため、運用中の疑問や不安にも対応してもらえます。
ファンドラップのデメリットと「大損した」と感じる原因
一方、ファンドラップでの運用を始めたことで「大損した」「失敗した」と感じる人もいるようです。
運用を始めてから後悔しないように、あらかじめファンドラップのデメリットや注意点を確認しておきましょう。
手数料や費用が高い
ファンドラップの最大の注意点は、大きなコストがかかりやすいところです。プロに資産の管理を任せるため、通常の投資信託や株式などでの投資に比べてコストが割高になりやすい点に注意しましょう。
ファンドラップでの投資にかかる費用には、以下のようなものがあります。
| 投資顧問報酬(投資一任手数料) | ファンドラップの運用や管理にかかる費用。「運用資産に対して〇%」という仕組みが多いが、報酬体系や料金の大きさは金融機関によって異なる。 |
| 信託報酬 | ファンドラップに組み込まれる投資信託の運用管理費用で、信託財産から別途差し引かれる。 |
| その他費用 | 取引手数料や為替手数料など金融機関が定める費用。 |
手数料の種類や大きさは金融機関によって異なるため、契約前にしっかりとチェックしておくことが肝心です。
また、ファンドラップには多数の投資信託が組み込まれていることも珍しくなく、中には非常に高い手数料の投資信託などが投資家の意向に反して組み入れられているケースも散見されるため注意しましょう。
NISA口座で購入できない
NISA(少額投資非課税制度)は、投資信託などから得られる運用益が非課税になるお得な制度です。
NISA口座を活用して資産運用に取り組んでいる人も多いですが、ファンドラップはこのNISA口座の対象外となっているため、課税口座での運用が基本となります。
そのため、運用によって得られた利益には20.315%の税金が課せられ、NISA口座の対象となる投資信託等と比べて不利に感じる場合もあります。
途中解約すると損失が発生しやすい
ファンドラップは中長期的な資産運用を前提としたサービスであるため、短期間で解約すると手数料負担が重く感じられるケースがあります。特に、運用開始から間もない段階での解約では、初期費用が回収できずに元本割れとなる可能性もあるでしょう。
また、金融機関によっては解約時に店舗への来店が必要であったり、解約手続きが煩雑であったりするため、「思っていたよりお金を自由に動かせない」と感じるかもしれません。
柔軟な資金管理を重視する方は、事前に解約の際のルールや手数料等も確認しておきましょう。
運用を始めるためにまとまった資金が必要
ファンドラップは、最低投資金額が数百万円からと設定されているケースが多く、少額から始められる投資信託と比べるとハードルが高いのが実情です。
一部ネット証券などでは、最低金額を引き下げたファンドラップサービスも登場していますが、対象商品や運用内容に制限があったり、手数料が割高に設定されていたりするケースもあるため、利用前に確認することが大切です。
自分に合った商品・コースを選ぶのが難しい
ファンドラップは契約時に行われるヒアリング結果に基づいて、リスクやリターンに応じたポートフォリオが提案されますが、必ずしもそれが自分にぴったり合うとは限りません。
また、年齢や家族構成が変化すると、リスク許容度や求めるリターンも変化しやすくなるため、ポートフォリオや運用方針は定期的に見直す必要があります。
しかし、ファンドラップでは「プロに任せている」という安心感でポートフォリオや運用方針の見直しをせずにほったらかしにしてしまいやすいため、自分のニーズと異なる運用になっていないか注意が必要です。
このようなミスマッチを防ぐには、定期的な見直しや専門家との相談が重要です。
プロに任せる意味がないと感じる可能性もある
ファンドラップのポートフォリオは、さまざまな投資対象が複雑に組み合わせられている印象を受けるかもしれませんが、実際には市販の投資信託を複数組み合わせただけの内容で、自分でも同じようなポートフォリオが簡単に作れる場合もあります。
市場の動きによっては期待するリターンが得られないこともあり、「これなら自分でやった方がよかったのでは?」と感じるケースもあるでしょう。
加えて、ファンドラップは対面証券会社で特におすすめされやすいですが、対面証券会社の窓口担当者は数年ごとに異動や転勤が発生するのが一般的です。
そのため、担当が代わるたびに新たな担当者と関係を構築しなくてはいけない点もデメリットに感じられるかもしれません。
ファンドラップの利用はどんな人におすすめ?
ここまで紹介したファンドラップのメリット・デメリットをもとに、どんな人にファンドラップでの運用が適しているのか確認していきましょう。
ファンドラップが向いている人
以下のような特徴に当てはまる人は、ファンドラップでの運用が適していると考えられます。
- ・投資初心者で知識や経験が少ない人
- ・家事や仕事が忙しく運用をプロに任せたい人
- ・自分の運用ニーズに合った商品を提案してほしい人
ファンドラップは、プロにポートフォリオの作成や運用資産の管理を任せられるというメリットがあります。
さまざまな資産への分散投資が手軽に可能なので、投資初心者の方や仕事や家事で忙しいという方に適しているでしょう。
ファンドラップが向いていない人
一方、以下のような人にはファンドラップよりも別の投資商品の方が適しているかもしれません。
- ・なるべくコストを抑えて効率よく運用したい人
- ・自分でもある程度投資の勉強を行っている人
- ・少額からコツコツ積立投資を行いたい人
ファンドラップは、投資信託や株式などシンプルな金融商品での運用に比べて、手数料や運用管理費用が大きくなりやすいというデメリットがあります。
なるべくコストを抑えて運用したいという方や自分で投資先を選びたいという方、毎月少しずつ投資金額を増やしていきたいという方は、ファンドラップではなく投資信託など別の金融商品の方が適しているでしょう。
迷ったらファイナンシャルプランナーに相談しよう
ファンドラップには数多くのメリットがある一方で、費用や運用スタイル、商品内容などの面で注意すべきポイントもあります。そのため、「自分にとって本当に向いているかどうか」を判断するには、家計全体を見渡した視点で検討することが重要です。
たとえば、「どれくらいの資産を投資に回しても大丈夫か」「老後資金や教育資金とどうバランスをとるか」などは、ライフプラン全体との関係も深いため、専門的な視点が役立ちます。
もし判断に迷ったら、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのも一つの方法です。FPは中立的な立場から資産運用についてのアドバイスをしてくれるため、ファンドラップ以外の選択肢も含めて、最適な方法を一緒に考えてもらえるでしょう。
まとめ:ファンドラップで大損しないために仕組みや注意点をしっかり理解しよう
ファンドラップは、投資のプロに運用を一任できる便利なサービスですが、手数料やサービス内容を理解しないまま契約すると「思ったより増えなかった」「損をした」と感じてしまう可能性があります。
大切なのは、メリットとデメリットをしっかり理解し、自分に本当に合った運用方法かどうかを見極めることです。
資産形成を成功させるためにも、必要に応じてファイナンシャルプランナーの力を借りながら慎重に検討するのをおすすめします。
マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
- ID:BM–695