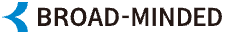持病があっても入れる保険とは?保険の選び方や対処法をわかりやすく解説
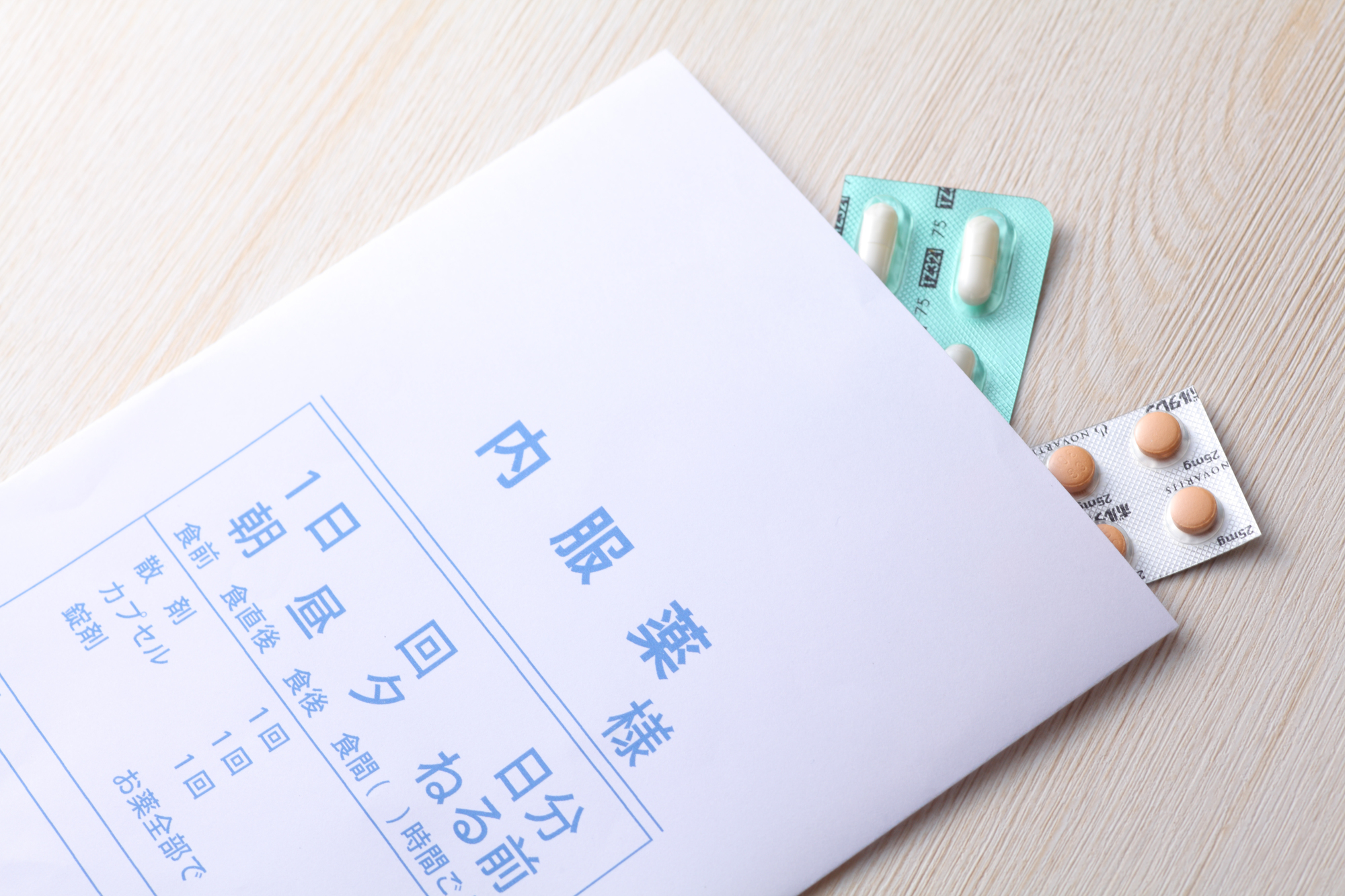 生命保険
生命保険
「病気になると保険に入れなくなるって本当?」「持病があっても入れる保険はあるのかな」現在病気の治療をしている方や過去に病気をした経験がある方は、このような不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。
そこでこの記事では、保険に加入できない病気の種類や病気になった方が保険に加入しづらくなる理由、そして持病がある方でも入れる可能性がある保険の種類について解説していきます。
また、持病がある方向けの保険のデメリットや持病がある方が保険を選ぶ際のポイントに関しても言及しているため、ぜひ最後まで読んで保険選びに役立ててください。
マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
保険に加入できない病気とは
加入を検討している保険の種類によって、加入できない病気の種類が異なります。
ここでは、死亡保険と医療保険のそれぞれに関して、加入できない保険の種類を解説します。
また、病気でなくても保険に加入できないケースが存在する点には注意が必要です。
死亡保険に加入できない病気
死亡保険に加入できない病気としては、主に以下のものが挙げられます。
<死亡保険に加入できない病気の一覧>
| 具体的な病名例 | |
| がん(上皮内がん※を含む) | 大腸がん、胃がん、肺がん、悪性リンパ腫、白血病 等 |
| 脳血管疾患 | 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血) |
| 心疾患 | 急性心筋梗塞、狭心症、重度の不整脈(ペースメーカー装着済みなど) |
| 精神疾患 | 統合失調症、双極性障害、アルコール依存症 |
| 腎疾患 | 慢性腎不全、ネフローゼ症候群 |
| 肝疾患 | 肝硬変、肝炎(B型・C型) |
| 指定難病 | パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
| 認知症疾患 | アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症 |
※初期のがんのことで手術によって完治するケースが多い
なお、保険会社によって診査基準は異なるため、上記の病気を経験したことがあっても、完治してから10年以上など、一定年数が経過していれば死亡保険に加入できる可能性があります。
反対に、上記で示した病気はあくまでも一例であり、上記に当てはまらない場合であっても加入が断られてしまうケースがあるため、注意しなければなりません。
医療保険に加入できない病気
医療保険に加入できない病気としては、先述した死亡保険で加入できない病気に加えて、以下のようなものがあります。
- ・糖尿病による合併症(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽、糖尿病性神経障害)
- ・関節リウマチ
- ・高血圧による合併症(高血圧性腎障害・腎不全、閉塞性動脈硬化症、高血圧性心肥大)
死亡保険は死亡や高度障害状態※に対する保障を準備するためのものですが、医療保険は入院や手術、通院等に対する保障を準備するためのものです。
※両目の失明や両手もしくは両脚の切断などの状態のこと
そのため、一般的に死亡保険よりも診査基準が厳しくなります。
ただ、先述したとおり保険会社によって診査基準は異なるため、加入前に専門家に相談すると良いでしょう。
病気でなくても保険に加入できないケースがある
病気でなくても、保険に加入できないケースがあります。それは主に以下のケースです。
- ・BMIが高い・低い
- ・数値が所定の基準値を超えている
- ・危険性の高い職業に就いている
BMIが高かったり低かったりすると、病気になる可能性が高いとみなされてしまうため、保険加入を断られてしまうことがあります。
ただ、健康診断結果を提出することで、他の数値に問題がないことを証明できれば加入できる可能性が高くなる場合があります。そのため、BMIの数値が通常値よりも外れている方は、健康診断結果も準備しておくと良いでしょう。
また、生命保険会社は各社で診査時における基準値を定めていますが、健康診断結果等に記載されている数値が所定の基準値を超えている場合は、保険加入を断られてしまうこともあるため注意が必要です。
加えて、格闘家やレーシングドライバー、高所作業者などの方は、他の方よりもケガ等をするリスクが高まるため、診査が厳しくなります。
病気になった方が保険に加入しづらくなる理由
病気になった方が保険に加入しづらくなるのには、いくつかの理由があります。生命保険会社の運営の仕組みや、契約者間の公平性を保つための方針が関係しています。
生命保険会社は「相互扶助の精神」によって運営されています。
相互扶助の精神とは、契約者間でお金を出し合って、誰かが困ったとき(保険金・給付金の支払事由に該当したとき)に集めたお金の中から保険金・給付金を支払う、といった仕組みを指します。
そのため、生命保険会社は「契約者間の公平性」に重きを置いているのです。
持病がある方は、健康な方と比較すると保険金や給付金を受け取る可能性が高くなります。そうなると、健康状態が悪い一部の方ばかりが保険金・給付金を受け取ることとなり、契約者間の公平性が保てません。
例えば、精神疾患を患っている方は、健康な方よりも自殺リスクや入院リスクが高いと考えられることから、加入不可とされるケースが多くなります。
このように、生命保険会社は保険金・給付金の支払いが一部の方に集中しないよう、基準を定めています。具体的には、所定の病気への罹患(りかん)歴がある方の加入を断ったり、保険料を多めに徴収したりして契約者間の公平性を保てるように調整しています。
病気になった方でも加入できる可能性がある保険とは
病気になったからといって、全ての保険に絶対に加入できないわけではありません。
多くの保険会社では、病気になった方に向けた以下の保険商品を提供しています。
- ・無選択型保険
- ・引受基準緩和型保険
それぞれの商品の特徴やメリットを見ていきましょう。
また、一般の保険に加入できる場合についても解説していきます。
無選択型保険
無選択型保険とは、告知をせずに加入できる保険のことをいいます。
通常、生命保険に加入する際には自身の現在の健康状態や過去にどのような病気になったのかを生命保険会社に申告(告知)する義務があります。
しかし、無選択型保険は一般の保険に加入が難しい方に向けて商品設計が行われた商品です。そのため、加入時に健康状態の告知は必要ありません。
このことから、現在病気治療中の方や過去に大きな病気を経験した人であっても加入できるだけでなく、告知が必要ないため申込手続きが簡便になるというメリットがあります。
引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険とは、一般の保険よりも診査基準が緩和された商品のことをいいます。
無選択型保険とは異なり申し込みの際に告知は必要となるものの、一般の保険と比較すると大幅に告知項目が少ないのが大きな特徴です。
告知項目は生命保険会社や保障内容によって異なりますが、以下のようなものが一般的です。
<引受基準緩和型保険の告知項目例>
|
引受基準緩和型保険は、これらの告知項目に対し全て「いいえ」と回答できる場合に限り、加入が可能となります。
告知を設けることで申し込みできる人を限定しているため、無選択型保険よりも保険料が抑えられることに加え、保障の範囲も広げられる点は覚えておきましょう。
一般の保険でも「条件付き」で加入できる場合がある
ここまで持病がある方向けの保険について解説してきましたが、病気の内容や現在の治療状況によっては、一般の保険に「特別条件」を付加した上で加入が認められるケースがあります。
特別条件として挙げられるのは、主に以下の4つです。
| 特別条件 | 内容 |
| 割増 | 支払う保険料が割増されること |
| 削減 | 加入から一定期間にわたって支払われる保険金・給付金額が削減されること |
| 特定疾病・部位不担保 | 特定の疾病や部位に対して入院や手術などによる治療を受けた場合でも保障が受けられないこと |
| 特定障害不担保 | 高度障害状態に対する保障がある保険、もしくは高度障害状態に該当した場合に保険料の支払いが免除される保険であるとき、生命保険会社があらかじめ指定した高度障害状態になったとしても保険金・給付金の支払いや保険料の払込免除を行わないこと |
これらの特別条件の程度は病気の内容によって異なり、例えば、5年間の削減の特別条件が付加された場合は、保険期間の経過ごとに下表の割合を乗じた保険金・給付金額が支払われます。
<特別条件による保険金・給付金の削減割合の例(5年間)>
| 保険期間 | 削減割合 |
| 1年目 | 1.5割 |
| 2年目 | 3.0割 |
| 3年目 | 4.5割 |
| 4年目 | 6.0割 |
| 5年目 | 8.0割 |
この場合、削減期間終了後(6年目以降)は、保険金・給付金の満額受け取りが可能です。
持病がある方向けの商品のデメリット
持病がある方向けの商品への加入を検討するにあたっては、デメリットも把握しておかなければなりません。
デメリットとして挙げられるのは、主に以下の4点です。
- ・保険料が高い
- ・保障内容が限定されている
- ・一般の保険よりも設定できる保険期間の柔軟性が低い
- ・加入から一定期間は保険金・給付金額が削減される
それぞれ解説します。
デメリット①保険料が高い
持病がある方は、保険金・給付金を支払う可能性が高い方であることから、生命保険会社としてもリスクヘッジを行わなければなりません。
そのため、一般の保険よりも保険料水準が高めに設定されています。
具体的に、40代男性が500万円の死亡保険に加入する場合、一般の保険と無選択型保険で月々どれだけ保険料に差があるのか見ていきましょう。
<死亡保険の保険料比較>
| 一般の死亡保険 | 無選択型死亡保険 |
| 約9,175円 | 約15,505円 |
上記の保険料は、一般的な保険会社のシミュレーションに基づく一例です。月々およそ6,300円、年間にするとおよそ75,600円もの差があり、無選択型保険の保険料水準がどれだけ高く設定されているかがわかります。
デメリット②保障内容が限定されている
一般の保険では、死亡保険や医療保険に加えて「生活習慣病に対する保障に特化したもの」や「がんに対する保障に特化したもの」など、さまざまな種類があります。
一方で、持病がある方向けの保険は、死亡保険や医療保険といった基本的な保障内容の商品が主流です。さらに、付加できる特約も限られてしまうのが現状です。
例えば、一般の医療保険に付加できる「通院特約」が、持病がある方向けの保険では用意されていないケースがあります。
しかし、近年では持病がある方向けに特約の種類が豊富な医療保険や、がんや糖尿病に特化した商品などが発売されているため、自身が備えたい保障が準備できる商品が見つかる可能性があります。そのため、自身が求める保障内容に基づいて、なるべく多くの保険商品から慎重に比較・検討することが重要です。
デメリット③一般の保険よりも設定できる保険期間の柔軟性が低い
生命保険には、一定期間の保障が準備できる定期タイプ(10年・20年、60歳まで・65歳までなど)と一生涯の保障が準備できる終身タイプがあり、一般の保険ではそれらが柔軟に選択できる商品が豊富にあります。
しかし、持病がある方向けの保険では終身タイプのみの取り扱いであったり、定期タイプであっても保険期間の選択肢が少なかったりする商品が多いのが現状です。
そのため、持病がある方向けの保険は一般の保険と比較して保険期間の柔軟性が低い点には気をつけましょう。
デメリット④加入から一定期間は保険金・給付金額が削減される
持病がある方は、加入直後に支払事由に該当するケースも少なくありません。
そのため、加入から1年間など、一定期間内は支払事由に該当したとしても支払われる保険金・給付金額が半額になる商品が多くなります。
中には契約直後から保険金・給付金を満額受け取れるものもありますが、それは削減期間が設けられている商品と比較して、保険料がより高額になる点には注意しましょう。
持病がある方が保険を選ぶ時のポイント
持病がある方が加入する保険を選ぶ際には、以下4つのポイントを意識しましょう。
- ・保障内容と保険料のバランスを考える
- ・持病の治療がひと段落してから加入する
- ・本当に一般の保険に加入できないのか確認する
- ・複数の保険会社の商品を比較する
それぞれ解説していきます。
ポイント①保障内容と保険料のバランスを考える
先述したとおり、無選択型保険や引受基準緩和型保険は、持病がある方を対象とした保険料設定となっているため、一般の保険と比較して保険料が割高になる傾向にあります。
また、持病がある方向けの保険は一般の保険よりも保障範囲が限定されるケースが多く、自分が備えたい保障がカバーされない、といったリスクも考えられます。
保険は「もしものとき」に備えて加入するものですが、必要以上の保険料をかけてまで必ず加入しなければならないものではありません。
それにもかかわらず「保険に加入したい」という気持ちが先行しすぎてしまうと、自分に適切でない保険を選んでしまう可能性が高くなります。
「自分はどのような保障を準備したいのか」を明確にしておくことで、加入しようとしている保険は自分に合った保障内容となっているのかを見極めやすくなるでしょう。
ポイント②持病の治療がひと段落してから加入する
持病の治療がひと段落してから加入することも検討しましょう。
一般の保険は、治療中の場合、加入を断られてしまったり、厳しい特別条件が付加されてしまったりする可能性が高くなります。
また、持病がある方向けの保険も、病気の内容によっては治療中だと告知項目にひっかかり加入できません。
ただ、完治してから数年経過後などは、一般の保険に無条件(特別条件が付加されない)で加入できるケースもあるため、ある程度治療が落ち着いたタイミングで保険加入を検討するのも一つの手です。
あらかじめ加入を検討している保険の告知内容等を確認しておくと良いでしょう。
ポイント③本当に一般の保険に加入できないのか確認する
本当に一般の保険に加入できないのか確認することも重要なポイントです。
先述したとおり、病気の内容や現在の治療状況によっては「特別条件付き」で一般の保険に加入できる可能性があります。
持病がある方向けの保険よりも一般の保険の方が保障範囲は広く、付加できる特約の種類も豊富なケースが多いです。
そのため「自分は一般の保険には入れない」と最初から決めつけないようにしましょう。
専門家に相談しながら、持病がある方向けの保険と特別条件が付加された一般の保険を比較し、検討することをおすすめします。
ポイント④複数の保険会社の商品を比較する
持病がある方向けの保険は、多くの保険会社が販売しています。
保険会社によって告知を求められる内容が異なることに加え、保険料にも差があります。
それだけでなく、加入後に保障内容を見直したくなった場合に、保険会社によっては保障の見直しができないケースもあるのです。
そのため、複数の保険会社の商品を比較し、より自分に適切な保険を選択するようにしましょう。
まとめ
この記事では、保険に加入できない病気の種類や病気になった方が保険に加入しづらくなる理由、持病がある方でも入れる可能性がある保険の種類とそのデメリット、持病がある方が保険を選ぶ際のポイントについて解説しました。
保険選びは、あなたやご家族の将来を守る大切なステップです。しかし、多くの保険商品や条件を理解し、自分にぴったりの保険を見つけるのは簡単なことではありません。
そんな時、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのも一つの手です。FPは保険の専門家であり、あなたの健康状態やライフスタイルに最適な保険プランを提案してくれます。適切な保険を選ぶことで、将来に対する備えをしっかり整えることができます。
マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
- ID:BM–647